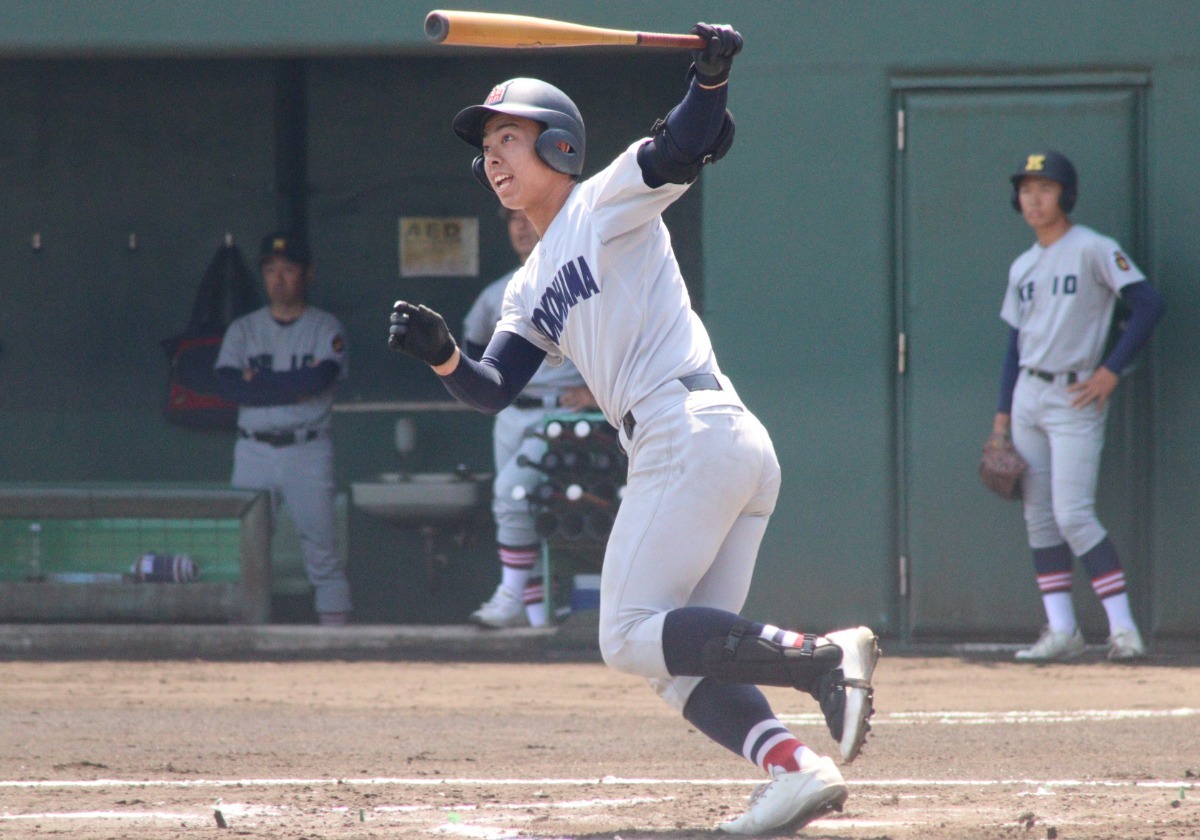音楽プロデューサーとしてCHEMISTRYやいきものがかりの結成・デビューなどで手腕を発揮する一方で、半世紀を超えるアマチュア野球観戦により野球の目利きでもある一志順夫。連載コラム「白球交差点」は、彼独自のエンタメ視点で過去と現在の野球シーンとその時代を縦横無尽に活写していきます。
大谷のホームランシーンに思わず箸が止まる昂揚感のある朝
大谷 翔平が絶好調だ。(7月12日現在打率.314、本塁打28、打点66、OPS1.026)三冠王も射程に捉えた勢いを持続している。それと呼応するかのように、過熱気味に繰り広げられる各局ワイドショーの「大谷翔平狂騒曲」。どれも似たような切り口で新鮮味に欠けるなぁと思いつつ、ホームランの映像シーンを目にすると図らずも箸が止まってしまう、そんな昂揚感を伴う朝の一コマは筆者だけに限った話ではないだろう。
テレビ的に大谷が今一番「数字を持ってる」存在であるのは明らかなので、こうしたメディアのステレオタイプな対応を批判するつもりは毛頭ないが、その様を見てなんとなくモヤモヤが晴れないのは、やはり根底にはここに至るまでの報道プロセス、つまり「メディアの掌返し」を是認しきれない筆者のルサンチマンがあるからだ。つまり、エンゼルス入団時、いや日本ハムから高卒ドラフト1位指名を受けた段階で、この未来を正確に予測できた野球評論家やメディア関係者はいったい何人いただろうか、という思いである。
2011年の夏甲子園で大谷を初めて肉眼で見て感じたロマンと将来性
筆者が初めて大谷を肉眼で見たのは、2011年夏の甲子園。対帝京戦である。花巻東の2年生投手に逸材がいるという噂はかねがね耳にしていたが、どちらかというとこのゲームの目当ては4番の松本 剛(日本ハム)、エースの伊藤 拓郎(元横浜DeNA)と1年生キャッチャー・石川 亮(日本ハム-オリックス)のバッテリーだった。この試合で途中登板した大谷は、成長痛からくる左足の負傷によりうまく下半身を使えない状態で、遠目からも明らかに苦心の投球ぶりがみてとれた。
試合は乱打戦のうえ松本の決勝打により決着したが、不調ながらも恵まれた体躯から繰り出される快速球はロマンと将来性を感じさせるには十二分だった。
翌年の選抜大会は、1回戦から大阪桐蔭のエース藤浪 晋太郎(阪神-アスレチックス-オリオールズ)との投げ合いが実現し注目を集めた。テレビ観戦ではあったが、かえってセンターカメラから見る大谷の球筋はスタンドからでは体感できない「凄み」がダイレクトに伝わってきた。特にスライダーの切れ味は、高校3年時の松坂大輔と双璧、いやそれ以上の魔球感があった。
さらにこの試合で最もインプレッシブだったのは、藤浪の内角スライダーを完璧にとらえたライトスタンドへのホームランだろう。今の二刀流の原点ともいえるスタイルがここに誕生したと言っても過言ではない。最後の夏は県大会決勝で敗れ、その勇姿を甲子園で見ることはできなかったが、準決勝の一関学院戦で記録した160キロは大谷の規格外のポテンシャルを示し、「大谷株」は高騰していく。
この時点でドラフト1位の評価は揺るがぬものになったのは確かだが、投手としてなのか打者としてなのかの判断については各球団スカウトの見解は分かれるところであり、当時の記事を見ても、投手派と打者派はほぼ二分されていて、スカウトの発言、コメントからも迷いが窺われる。積極的に二刀流に挑戦させてみては、という意見はほぼ見当たらない。
それはもっともな話で、二刀流の成功事例は極めて少なく、筆者が記憶しているだけでも1970年代以降は永淵洋三(佐賀=現佐賀西-東芝-近鉄-日本ハム)、外山義明(天理-クラレ岡山-ヤクルト-ロッテ-南海=現ソフトバンク)くらいで、しかも多分に話題作りの側面が強く、実質的な取り組みとは言えなかった。ジャンボの愛称で親しまれた仲根正広(日大桜丘-近鉄-中日)、島本講平(箕島-南海-近鉄)、畠山準(池田-南海-大洋=現DeNA)あたりは正確には転向組、最近だと高井雄平(東北高-ヤクルト)もこのカテゴリーに入る。二刀流前提で入団した矢澤宏太(日大藤沢-日本体育大-日本ハム)も今は専ら投手、今後の起用法は霧の中である。