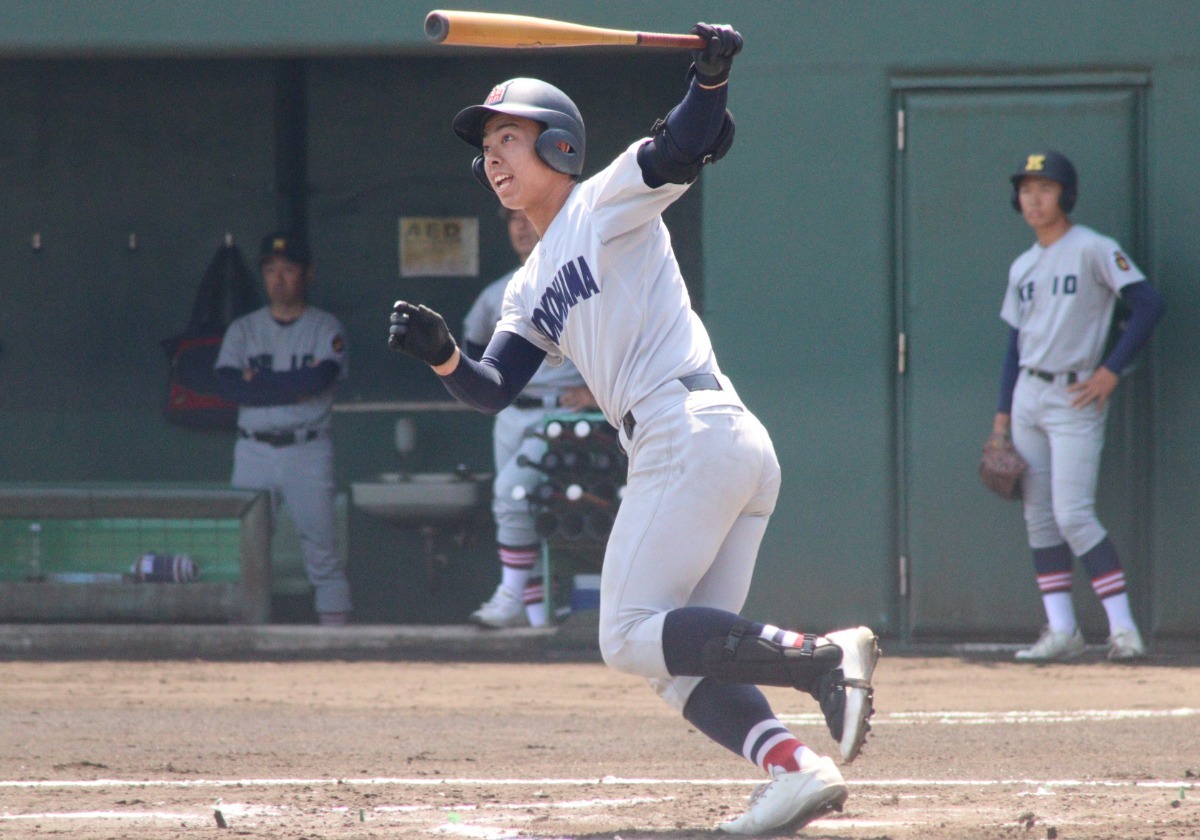2020年4月に創立された山梨県の青洲は、2021年の夏までは連合チームで大会に参戦。その秋から単独で出場するようになると、2024年の秋まででベスト8に5度勝ち上がった。山梨で急速成長し続ける新進気鋭の学校だが、その背景に迫っていくと、多くの支えに助けられながら、チームを作り上げている途中にあった。
甲子園出場校などの再編で生まれた創部4年目の新鋭。地域、OBの支えを力に
青洲は甲府市より南に15キロほど離れた場所に位置する、西八代郡市川三郷町にある。人口は14,505人の自然豊かな地域で、センターの後ろには多くの山々がそびえ立っていた。
2学年で、選手27人で活動している青洲のグラウンドのバックネット裏には、3つの記念碑が置かれている。そこにかかれているのは「甲子園出場記念」という大きな文字とともに、当時のメンバーの名前が並んでいる。
単独出場が始まって4年目の青洲は、まだ甲子園出場実績がない。にもかかわらず、「甲子園出場記念」の記念碑はどうして置かれているのか。青洲は、増穂商、市川、峡南の3校が再編されたことで誕生した学校で、その3校のうち、市川と峡南は甲子園に出場した実績がある。
春夏合わせて市川は5回、峡南は2回の甲子園出場実績を持っていた古豪。そのときに置かれた記念碑が、青洲のグラウンドにあるというわけだ。

だから、「(当時のことを)思い出すことはありますね」と、青洲の指揮官を務める佐野大輔監督は懐かしそうに振り返る。自身も市川の野球部で3年間を過ごして甲子園も経験。1991年、第71回大会でベスト8まで進出したが、「地元の方々が応援してくれたのはありがたかったですね」と地域へ支えに改めて感謝していた。
そんな伝統を持っていた母校だが、2016年には再編されることが報じられていた。既に教員として、山梨県内の公立校で指導にあたっていた佐野監督。当然、母校の知らせは耳に入った。
「当時は寂しいというのが一番でした」と佐野監督は話すが、OB会も気持ちは同じ。母校の名前が無くなってしまう寂しさを感じているように佐野監督の目には見えたそうだが、それは現場が活気づいていたことも大きいだろう。
2016年秋、県大会で準優勝を果たして、関東大会に出場。初戦で千葉の中央学院に敗れたとはいえ、県内有数の実力校として力を示していた。そんなときに再編が決まったのだから、思うところもあるだろう。
ただ実際のところ、青洲がある峡南地域は、中学生がそこまで多くない状況のようだ。

地元の公立中学から青洲に進学してきた主力選手・松野丈成内野手(2年)は、中学時代をこう振り返る。
「いまの青洲より全然少なかったです。1学年50人くらいで、2クラス。それが3学年で150人くらいの学校のところで、野球をやっていました。なので、選手は9人ギリギリ。3年生になって15人前後になりましたが、9人の時は寂しかったですね。その分、1人1人が個性は発揮できて楽しかったんですけど」
この現状は佐野監督も感じる部分があるという。
「中学軟式を見ると、本当にすごく少なくなってきたと感じます。実際、合同チームで大会に出場するところが増えていて、ときには県大会の決勝戦に合同チームが勝ち上がってくるケースもあります」
こうした地域の状況があったことを考えると、「全体を考えると、仕方なかったかもしれない」と佐野監督は寂しさと同時に現実を受け入れていた。こうした厳しい状況だからこそ、地域に対しての感謝の思いを、佐野監督は忘れていない。
「現役時代だけでなく、今も歩いていたら声をかけてもらうたびに力をもらっています。監督に就任してからも、地域から差し入れをたくさん持ってきてくれたり、応援にも来てもらったり、多くの方が支えてくれて本当に感謝しています。
小さい町ですけど、地元の子どもが来ていますし、甲子園に出れば盛り上がると思うんです。それでいろんな人たちの力になればいいと思うんです。普段、自分たちが力をもらっているので」
夏はケガで離脱したが、新チームでは主力投手として活躍が期待される中嶌久翔投手(2年)も、佐野監督同様に「自分は知らない方だったんですが、声をかけてもらうことがあって、『頑張ろう』という気持ちにはなりました」と地域の力を感じることがあったという。

佐野監督、そして松野の話すように、青洲のある市川三郷町だけでなく、山梨県全体の中学軟式も、厳しい現実にあるのは間違いない。それでも地域が支えてくれるからこそ、佐野監督は地域と一体となって青洲を引っ張れているのだろう。
ただもちろん、再編となった3校の思いも力になっている。
「閉部式でも市川、増穂商、青洲合わせて卒部生が200人近く来て下さいました。峡南だけ現役選手がいなかったんですけど、現役選手もきてくれましたが、私たち指導者はそういったOB・OGたちの思いを背負ってやろうと思っています」
新チームから主将になった山土井来斗外野手(2年)も、父が市川OBであり、佐野監督の同級生。進学する際は、「(OBの息子とか関係なく)1人の青洲の選手として頑張れ」と声をかけられたが、中学生の頃から父と一緒に夏の大会に応援に行くことが増えていた。
そのなかで次第に、「少しずつ父の母校だと認識が強くなってきた」という。佐野監督にも小学4年生の時に会っており、山土井は市川、そして青洲とは何かと縁がある。秋の大会に向けて「関東大会に出場する」と宣言した。そこには青洲としての結果を出したいのはもちろんだろう。だがどこかに、OBたちへの思いもあるのではないだろうか。
佐野監督、そして選手たちは3校の先輩たち、さらに地域の思いや支えを感じながら、4年目のスタートを切ることができた。とはいえ、まだ青洲の歴史は始まったばかり。これから歴史を紡ぎ、伝統・文化を作っていくチームだ。果たして、これからどんな歴史を刻んでいくのだろうか。