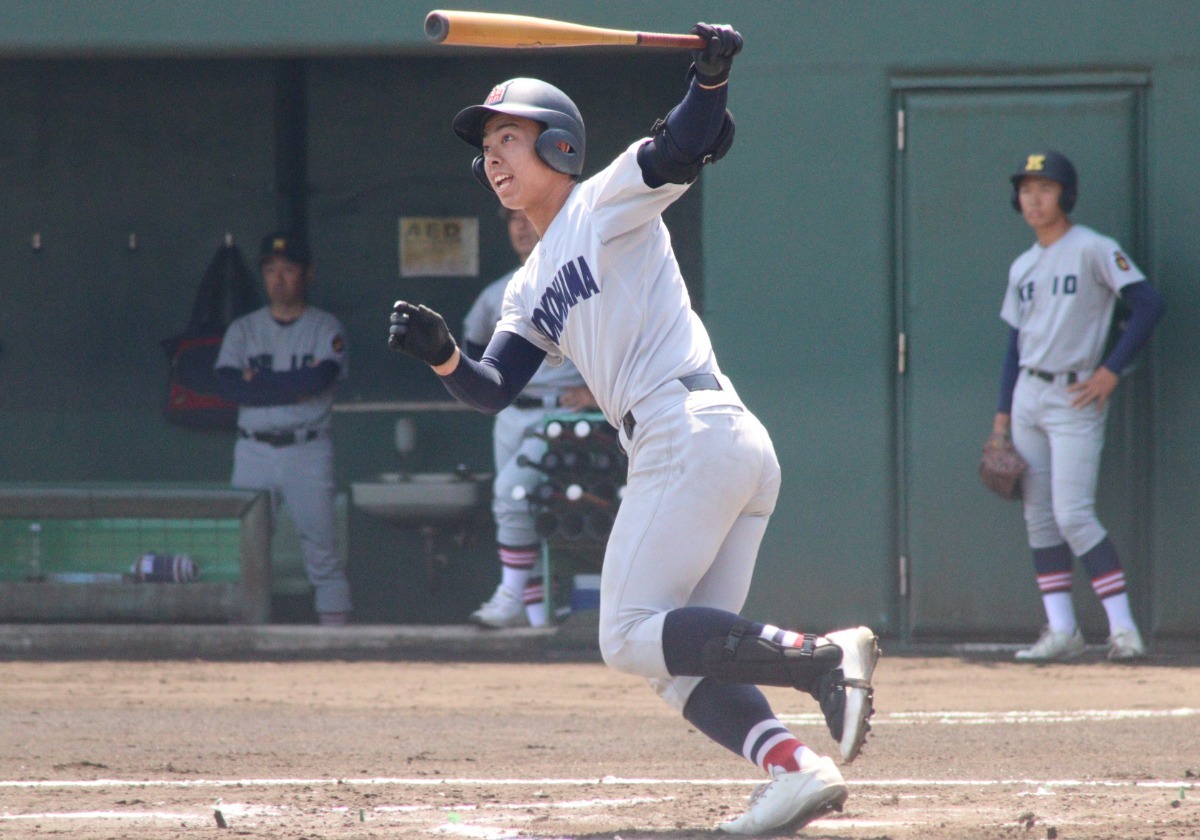音楽プロデューサーとしてCHEMISTRYやいきものがかりの結成、デビューなどで手腕を発揮する一方で、半世紀を超えるアマチュア野球観戦により野球の目利きでもある一志順夫。連載コラム「白球交差点」は、彼独自のエンタメ視点で過去と現在の野球シーンとその時代を縦横無尽に活写していきます。
スロースタートの球春到来風景も様変わり、準備万端かつ合理的で洗練された現代キャンプ
つい最近まで新年の挨拶をしていたと思ったら、早いものでもう2月。プロ野球もキャンプインし、いよいよ球春到来間近となった。
キャンプ地までは足を運べないが、今はCS放送やら動画配信で各チームの動向が窺えるのは便利でありがたい。昔と違って令和の選手は年明け早々から自主トレで入念に体作りをしてくるので、キャンプ初日からブルペンに入り全力投球する姿も珍しくなくなった。紅白戦も第1クールから始まったり、こういうところからも現代野球の様変わりを実感する。
昭和時代のキャンプは令和の現在と比較すると劣悪な設備や環境下で運営されていて、今では信じがたい実態も数々あった。例えば、まずオフ以降の体調管理は基本的に選手任せ、自主トレも名ばかりでキャンプインまでの私生活はやりたい放題、選手はオーバーウェイト状態でキャンプ地入りするのが当たり前、よってキャンプ前半は走り込みによる贅肉落としがメインだった。
江夏 豊、田淵 幸一、遠井 吾郎などのでっぷりした体躯を見て「阪神部屋」などと揶揄するスポーツ紙の見出しも年中行事のデフォルト。宿泊施設のホスピタリティもないに等しく、若手選手は大部屋での雑魚寝でプライバシーの概念もなかった。これも現代のコンプラ上ではあり得ないが、首脳陣と選手が賭け麻雀にうつつを抜かす姿をスポーツ紙が何の躊躇いもなく報道していたのはもはや笑えるレベルだ。
キャンプ地そのものも今こそ沖縄、宮崎に集中しているが、当時は高知はまだしもなぜかさほど温暖とはいえない呉、奈良、明石などでも行われていた。甲子園球場、神宮球場、川崎球場、中百舌鳥球場など前半は本拠地で仕上げてから九州・四国の各地に移動するパターンも多く、実質的に今の自主トレの内容がこの時期にディレイしていたことがわかる。キャンプ風景も寒々しく、実際に雪の中で練習している姿も稀ではなかった。経費など予算の問題があったのだと思うが、いずれにしろ合理的で洗練された現代キャンプ事情とは隔世の感がある。その意味で今の選手は野球に集中できるし、高待遇で恵まれているなあ、とつくづく思う。
令和時代のキャンプの平均的チーム負担経費は約1.5億円とされている。それぞれのキャンプ地にはのべ20〜30万人が訪れるといわれており、受け入れる自治体側のメリットは、税収含めた観光収入の見地からも決して小さくない。誘致にも力が入るというものだろう。とはいえ、しょせん12球団レベルの話。MLB並みの球団数が揃わないと、波及的経済効果の意味合いで地方自治体活性化のスケールメリットを感じにくいのが課題である。まずはこれまで幾度となく議論されてきた16球団構想の実現に向けて本格的な取り組みをするべきというのが筆者の持論でもあるのだが、これについてはまた稿を改めたい。